第12回:濃度と密度
濃度や密度の問題は、みんなあまり好きではないですよね。
もう少し言うと、濃度や密度に限らず、割合を表す陵の取り扱いが苦手な人が多いようです。
これらの値は足したり引いたりすることができないし、その値が出てくるとたいてい単位が変わってしまうからイメージがしにくいのではないかと思います。
でも、ちょっと難しい問題には濃度や密度が入っているし、どうしても避けては通れない重要な値ですよね。
今回は、濃度や密度のイメージを作りながら、その使い方になれていきましょう。
密度
密度とは、単位体積当たりの質量の事です。単位体積とはその問題でつかう体積の単位で1体積の事です。例えばある問題で、体積をcm3で表していたら、その問題での単位体積は1cm3ということになります。
つまり、ある物体があって、その物体の1cm3の質量がAgだったとすると、密度はA g/ cm3となるわけです。
では、体積νcm3、Bgの物体があったら、その密度は何g/ cm3となるでしょうか。
ちょっと考えればわかりますよね。この問題では単位体積は1cm3です。νcm3でBgなのですから、1cm3の質量は、![]() gですよね。つまり、この物体の密度は
gですよね。つまり、この物体の密度は![]() g/ cm3なのです。
g/ cm3なのです。

次に、この物体と同じ物質で構成されているUcm3の物体の質量を求めてみましょう。この物体を構成している物質は1cm3あたりの質量が![]() gですね。この物質がUcm3あつまってできているわけですから、その質量は、
gですね。この物質がUcm3あつまってできているわけですから、その質量は、![]() ×U gになりますよね。
×U gになりますよね。

どうですか?密度についてのイメージができましたか?では、ちょっと計算の練習をしてみましょう。
例題
- 100m3で2000kgの物質の密度は何g/cm3か。
- 1)の物質10ℓの質量はいくらか。
(解説・解答)
単位の取り扱いに注意しましょう。
1m=100cmですから、1m3=1003cm3=106cm3です。
また、1kg=103gですから、2000Kg=2×106gです。
したがって、この物質の密度は 2×106g÷106cm3=2.0g/cm3となります。1ℓ=1000cm3ですから、10ℓ=104gです。
したがって、この物質10ℓの質量は、2.0×104gとなります。
ちなみに、化学ではg/cm3やg/mlがよく用いられます。
濃度(モル濃度、質量モル濃度、質量パーセント濃度)
化学で用いる濃度は、体積モル濃度、質量モル濃度、質量パーセント濃度の3種類です。体積モル濃度は容量モル濃度あるいは単にモル濃度、体積モル濃度は重量モル濃度とも言います。
濃度は、溶液の量と溶質の量の割合を表したもので、溶液の量と溶質の量を結びつけます。
(1) 質量パーセント濃度
質量パーセント濃度は、溶液の質量にたいして溶質の質量がどれくらい含まれているかを表すもので、100gの溶液中に含まれる溶質の質量(g)を表します。

(2) (体積)モル濃度
体積モル濃度は、溶液1ℓに溶質が何mol含まれているかを表すもので、化学では最も良く使う濃度の単位です。

(3) 質量モル濃度
質量モル濃度は、溶媒1㎏に溶質が何mol含まれているかを表すもので、凝固点降下、沸点上昇などを計算するときに用いられる濃度の単位です。

密度に引き続いて濃度のイメージもできましたか?
それでは、計算練習をしてみましょう。
例題)
- 0.50mol/ℓのNaOH水溶液500mℓがある。この水溶液中のNaOHの物質量を求めなさい。
- 0.50mol/ℓのNaOH水溶液の密度を1.0g/mℓとする。この水溶液の質量パーセント濃度を求めなさい。
- 質量モル濃度が4.00mol/kgの水酸化カリウム水溶液60gに、水40gを加えたら、密度が1.17g/mℓの水溶液になった。モル濃度はいくらか。K=39 、O=16、H=1としてよい。
(解説・解答)
0.50mol/ℓというのは、溶液1ℓに溶質が0.50mol溶けているという意味ですね。
そして、この水溶液は500mℓ= ℓです。
ℓです。
よって、この水溶液に溶けている溶質NaOHの物質量は0.50× =0.25molです。
=0.25molです。ここで使った

という式は、今後何度も使いますから、覚えておきましょう。
いわゆる濃度の単位変換の問題です。濃度変換は難しい問題に分類されているようですね。大学生でもできない人を見かけます。ただ、これはコツを知っていれば簡単です。
濃度変換のステップ
1)変換後の濃度の定義式を書く。
2)1)で書いた定義式に出てくる量を求める。
3)2)で求めた値を、定義式に代入して計算する。
※ 溶液の量が分からないときは1ℓで考える。では、変換後の濃度の定義式を書きます。

この式を見ると、質量パーセント濃度を求めるためには、溶質の質量と、溶液の質量が分かれば良いことがわかります。
与えられた条件から溶質の質量と、溶液の質量が求まらないか考えてみますが、どちらもこの溶液の量が分からないと求めようがなさそうです。
そこで、1ℓの溶液を仮定して考えます。濃度は溶液の量によりませんから、100ℓで考えても、1μℓで考えても濃度は同じですから、都合のいい量を仮定すればいいわけです。まず、溶質の質量から求めます。モル濃度が0.50mol/ℓですから、この溶液の中に入っている溶質の物質量は、0.50mol/ℓ×1ℓ=0.50molですね。
NaOHの式量は40ですから、溶質の質量は0.50(mol)×40=20gとなります。
つぎに、溶液の質量を求めます。1.0g/mℓの溶液が1ℓ=1000mℓありますから、溶液の質量は、1.0×1000=1000gとなります。
最後に、これらの値を最初に書いた定義式に代入すれば、質量パーセント濃度が求まります。

モル濃度を求めるのに必要なのは、溶液の体積と溶質の物質量でしたね。溶質の物質量は濃度が分かっていますから簡単に求められそうですが、問題は溶液の体積です。
まず、溶質の物質量から求めましょう。希釈する前後で溶質の物質量は変わりませんから、希釈する前の条件で考えます。
溶液に含まれるKOHの物質量をχmolと置きます。この質量は56χgです。
すると、溶媒の質量は60-56χg=(60-56χ)×10-3kg

ここへ代入すると

これを解くと、

次に、溶液の体積は、40+60=100gですから。
溶液の密度は1.17g/mℓなので溶質の体積は (mℓ)となります。
(mℓ)となります。よって、モル濃度は

最後に、0.10mol/ℓのNaCl水溶液100mℓを正確に作る方法(調製と言います。)について説明します。
0.10mol/ℓの水溶液ですから、100mℓの水溶液中に溶質のNaClは0.010mol溶けていればいいことになります。
そこで、0.010molのNaCl(式量58.5) 正確に量りとって、水に溶かして100mℓの水溶液にします。
NaClの式量は58.5ですから、0.010×58.5=0.585gですね。
このとき、正確に水溶液の体積を100mℓにするためにメスフラスコという器具を用います。メスフラスコは、下図のような器具で、細長くなった首のところに標線と呼ばれる線が入っていて、この線まで水を入れると、正確な体積の溶液を作ることができます。

小さなビーカーで液体のNaClを蒸留水に溶かし、ろうとを使ってメスフラスコに入れます。NaCl水溶液をメスフラスコに入れた後、ビーカーを蒸留水で洗い、洗った液も一緒にメスフラスコに入れます。これは、残った溶液に含まれているNaClを回収するためです。
メスフラスコに蒸留水を入れて水面が標線の所に来るようにすれば、100mℓの0.10mol/ℓNaCl水溶液の完成です。
これを絵にまとめると次のようになります。

ちなみに、メスフラスコは使用前に洗いますが、ぬれたまま使ってもかまいません。どうせ、その後で蒸留水を加えるわけですから。
さて、今日はこれでおしまいです。次回からは化学反応式を使った問題の解き方について説明していこうと思います。
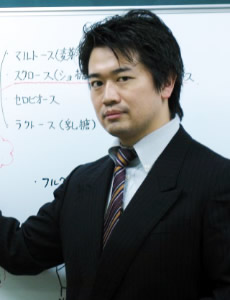
平野 晃康
株式会社CMP代表取締役
私立大学医学部に入ろう.COM管理人
大学受験アナリスト・予備校講師
昭和53年生まれ、予備校講師歴13年、大学院生の頃から予備校講師として化学・数学を主体に教鞭を取る。名古屋セミナーグループ医進サクセス室長を経て、株式会社CMPを設立、医学部受験情報を配信するメディアサイト私立大学医学部に入ろう.COMを立ち上げる傍ら、朝日新聞社・大学通信・ルックデータ出版などのコラム寄稿・取材などを行う。

