第15回:酸と塩基(2)
今回は酸性・塩基性(まとめて液性といいます。)の度合いを表すのに用いるpHについて説明します。
酸性はH+の性質、塩基性はOH-の性質の事でしたね。ですから、酸性の強さを表すにはH+の濃度、塩基性の強さを表すにはOH-の濃度を考えればよさそうです。
でも、溶液の性質を表すのに、酸性のときはH+、塩基性になるとOH-の濃度を考えるのではちょっと不便ですね。できればどちらかに統一したいものです。
実は、水中のH+の濃度[H+]とOH-の濃度[OH-]の間には、[H+]×[OH-]=10-14(mol/ℓ)2という関係があります。この値のことを、水のイオン積といって、25℃の水溶液では、その水溶液の種類によらず必ず成り立つ関係式です。
この式を変形すると、[H+]=![]() (mol/ℓ)となりますから、[OH-]から[H+]を求める事ができます。これを使えば、[OH-]を用いなくても、[H+]の濃度だけで液性を表す事ができます。
(mol/ℓ)となりますから、[OH-]から[H+]を求める事ができます。これを使えば、[OH-]を用いなくても、[H+]の濃度だけで液性を表す事ができます。
それでは、酸性・塩基性のときに[H+]がどのような値を取って変化するのか計算してみましょう。
まず、[H+]や[OH-]がどんな値を取るのか考えてみましょう。[H+]>[OH-]のときが酸性、[H+]<[OH-]のときが塩基性ですね。中性は[H+]=[OH-]の時ですから、[H+][OH-]=[H+]2=10-14(mol/ℓ)2より[H+]=10-7(mol/ℓ)の時です。
ということは、10-7(mol/ℓ)より[H+]が大きいときは[H+]>[OH-]となり酸性、小さいときは[H+]<[OH-]となって塩基性です。

このように表にしてみるとわかりますが、[H+]はとても大きな幅で変動します。例えば強酸性の10-1(mol/ℓ)から強塩基性の10-13(mol/ℓ)まで動くと、[H+]は1000000000000分の1の大きさになりますし、10-1(mol/ℓ)から10-3(mol/ℓ)に変化しただけでも100分の1になるわけですから、もし、これをグラフに描いたとすると、下のようにほとんど読み取る事ができないようなグラフになってしまいます。

そこで、log10を取って、[H+]の指数だけを調べる事にします。log10[H+]では値が負になってしまいますから-をつけて、-log10[H+]とします。この値をpHといいます。
pH = -log10[H+]
すると、[H+]とpHの関係は下表のようになります。また、NaOH滴下量に対して[H+]ではなくpHを縦軸にとってグラフを描くと、pHは[H+]の値がどんなに変化してもpHは1~14の間を動くので下図のようにちゃんと読み取ることができるグラフになります。

中性は[H+]=10-7(mol/ℓ)の時でしたが、このときはpH=7ですから、この値より大きいと塩基性、小さいと酸性と言うことになります。
pH <7 ・・・・ 酸性
pH =7 ・・・・ 中性
pH >7 ・・・・ 塩基性
◎数字が大きいほど塩基性が強く、数字が小さいほど酸性が強い。
では、ここでpHの計算の練習をしましょう。
例題
次の(1)~(5)の水溶液のpHを求めなさい。
- 0.010 mol/ℓ HCl 水溶液(電離度1)
- 0.050 mol/ℓ H2SO4 水溶液(電離度1)
- 0.040 mol/ℓ CH3COOH 水溶液(電離度0.025)
- 0.010 mol/ℓ NaOH 水溶液(電離度1)
- 1.0×10-5 mol/ℓ HCl 水溶液を1000倍に希釈した水溶液の[H+]を求めよ。
解説・解答
まず、電離度が目に付きますね。電離度とは溶質がどれくらいの割合で電離するかを表すものでした。例えば電離度1であれば、全ての溶質が電離します。一方、電離度0.5ならば溶質の半分が電離、0.25であれば溶質の25%が電離します。
(1) 0.050 mol/ℓ HCl 水溶液(電離度1)
溶液のpH を計算するには、まず[H+]の濃度を求めます。
電離度が1ですから、全てのHClが電離します。
また、価数が1ですから、1つのHClから放出されるH+の数は1つです。
よって、【HClの濃度】=【H+の濃度】になります。
[H+]=[HCl]=0.010mol/ℓ
∴ pH=-log100.010=2.0
(H+の濃度) = (酸の濃度)×(電離度)×(価数) となります。
【解説】
(酸の濃度)×(電離度)を計算すると、電離した酸の濃度が分かります。
例えば、電離度0.025の0.10mol/ℓ H3PO4であれば電離しているH3PO4の濃度は0.10mol/ℓ×0.025=2.5×10-3mol/ℓ・・・(1)となります。
酸が電離すると、1分子から価数に等しい数のH+が放出されますから、
(酸の濃度)×(電離度)×(価数)がH+の濃度となるわけです。
(1)の例ならば、[H+]=0.10×0.025×3=7.5×10-3mol/ℓ
塩基の場合は(OH-の濃度) = (塩基の濃度)×(電離度)×(価数) です。
(2) 0.050 mol/ℓ H2SO4 水溶液(電離度1)
[H+]=(酸の濃度)0.050×(電離度)1×(価数)2=0.10 mol/ℓ
∴ pH=-log100.10=1.0
(3) 0.040 mol/ℓ CH3COOH 水溶液(電離度0.025)
弱酸ですから、全て電離するわけではありません。
[H+]=(酸の濃度)0.040×(電離度)0.025×(価数)1=0.0010mol/ℓ
∴ pH=-log100.001=3.0
(4) 0.010 mol/ℓ NaOH 水溶液(電離度1)
塩基の濃度から直接[H+]を求める事はできません。まず、[OH-]を求めてから、水のイオン積を使って[H+]を求めます。
[OH-]=(塩基の濃度)0.010×(電離度)1×(価数)1=0.010mol/ℓ
水のイオン積より[H+]=![]() =
=![]() =10-12mol/ℓ
=10-12mol/ℓ
∴ pH=-log1010-12=12
(5) 1.0×10-5 mol/ℓ HCl 水溶液を1000倍に希釈した水溶液
1.0×10-5 mol/ℓ HCl 水溶液の[H+]は10-5(mol/ℓ)ですから、これを1000倍に希釈したので、[H+]=10-8(mol/ℓ)としてしまいそうです。
しかし、1.0×10-5 mol/ℓ HCl 水溶液は酸ですから、これをどんなに希釈しても塩基性になるわけがありませんね。
実は、酸を希釈したときに、酸が放出するH+の濃度が10-7(mol/ℓ)に近い値、あるいはそれ以下になってしまう時は水の電離によるH+の濃度を無視することができなくなります。
水の電離によるH+の濃度をχ(mol/ℓ)とすると、水の電離はH2O → H++OH-ですから、水の電離によって生じるOH-の濃度もχ(mol/ℓ)です。
よって、この水溶液は[H+]=χ+10-8(mol/ℓ)、[OH-]=χ(mol/ℓ)となります。水のイオン積を使ってχを求めましょう。
[H+][OH-]=10-14(mol/ℓ)2 より(χ+10-8)χ=10-14(mol/ℓ)2
整理すると、χ2+10-8 χ -10-14 = 0 となります。

よって、[H+]=χ+10-8=1.05×10-7 (mol/ℓ)
(※)の変形について。
hが1より十分に小さい値の時、(1+h)n≒1+nhが成立します。
この近似は良く使うので、覚えておきましょう。
さて、以上でpHの説明はおしまいです。次は、中和点におけるpHと滴定曲線について説明します。滴定曲線というのは、酸に対して塩基を、あるいは塩基に対して酸を加えたときに起こるpH の変化を、縦軸にpHを、横軸に塩基あるいは酸の滴下量を取って表したグラフのことです。
塩基を酸に加えた場合の滴定曲線を下図に示します。滴定曲線には3つのパターンがあります。

強酸-強塩基:中和点のpHはほぼ中性で、大きなpHjump
強酸-弱塩基:中和点のpHは酸性で、小さなpHjump
弱酸-強塩基:中和点のpHは塩基性で、小さなpHjump (中和点は、強いほうに偏る。)
それぞれ、pHが大きく動く点がありますね。これをpHjumpといい、このpHjumpの真ん中の点を中和点と言います。中和点は酸の放出するH+と塩基の放出するOH-の数が等しくなった点で、酸と塩基が完全に反応して水と塩の水溶液になる点です。
中和点・・【酸の放出するH+の物質量】と【塩基の放出するOH-の物質量】が等しくなる点
3つのパターンを見てもらうと分かるように、(1)の場合は中和点がほぼ中性ですが、(2)と(3)ではそれぞれ中和点が酸性と塩基性にずれていますね。中和反応によって酸と塩基は反応してなくなってしまい、塩の水溶液になっているのに、なぜ、酸性や塩基性にずれるのでしょうか。実は塩は中性の物質ばかりではなく、酸性や塩基性のものがあるのです。
塩の水溶液が中性になるか酸性になるか塩基性になるかは、その塩がどのような酸・塩基の組み合わせで生じるかによって決まります。
強酸と強塩基の塩は中性 ・・ 例)NaCl、CaCl2、Na2SO4
弱酸と強塩基の塩は塩基性 ・・ 例)CH3COONa、Na2CO3、NaHCO3
強酸と弱塩基の塩は酸性 ・・ 例)NH4Cl、FeCl3
上の表のように、強いほうの性質が現れる、と考えてもらえばOKです。次回はこの塩の分類や性質についてもう少し詳しく説明します。また理論的な説明は、塩の加水分解(化学II)のところで説明します。
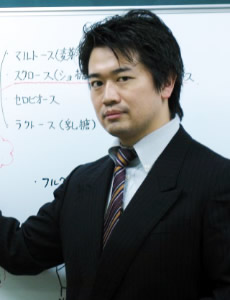
平野 晃康
株式会社CMP代表取締役
私立大学医学部に入ろう.COM管理人
大学受験アナリスト・予備校講師
昭和53年生まれ、予備校講師歴13年、大学院生の頃から予備校講師として化学・数学を主体に教鞭を取る。名古屋セミナーグループ医進サクセス室長を経て、株式会社CMPを設立、医学部受験情報を配信するメディアサイト私立大学医学部に入ろう.COMを立ち上げる傍ら、朝日新聞社・大学通信・ルックデータ出版などのコラム寄稿・取材などを行う。

