化学講座 第39回:気体の分子量測定
理想気体の状態方程式を利用して気体の分子量を求めることができます。
例えば、P (Pa)、V (L)、T (K) で、気体の質量が ![]() だった場合、気体の分子量を M とすると、理想気体の状態方程式を使って、
だった場合、気体の分子量を M とすると、理想気体の状態方程式を使って、![]() が成立します。
が成立します。
ここで、Mについて解くと、![]() となりますから、気体の分子量を求めることができます。
となりますから、気体の分子量を求めることができます。
理論としては簡単なのですが、実際に計算するには、気体の圧力P (Pa)、体積V (L)、温度T (K)、質量![]() 等を測定する必要があります。
等を測定する必要があります。
その方法として、高校では、1 ) 水上置換法 2 ) デュマ法 3 ) ビクトルマイヤー法などが紹介されています。
1 ) の水上置換法は、水を満たしたメスシリンダーを水槽に直立させて、そこにガスボンベなどから試料の気体を注入して、気体を入れたらメスシリンダーを上下に動かして、中の液体と外の液体の表面の高さが同じになるように調節します。
この時点で、ボンベの質量の変化から気体の質量が分かります。また、水面が同じであれば圧力は等しい(メスシリンダー内の圧力が大気圧と同じなので液面が等しくなっているわけです。)ので、大気圧を測定すれば、気体の圧力も分かります。また、実験装置は全て室温になっているので、室温を測定すれば、気体の温度もわかります。
ここで、ちょっと気を付けなくてはいけないのは、メスシリンダー内の圧力は大気圧と等しくなっていますが、水と接触しているので、メスシリンダー内は試料の気体のほかに飽和水蒸気に満たされているという事です。
従って、気体の圧力は ( 大気圧 ) - ( その温度での飽和水蒸気圧 ) で計算しなくてはいけません。
水の表面張力によってメニスカスが生じる事やメスシリンダーを用いるために測定精度はそれほど高くありませんがこのように比較的簡単に気体の分子量を測定することができるのです。
1 ) 水上置換法


2 )デュマ法
2 ) のデュマ法では、丸底フラスコに小さな穴の開いたアルミ箔のふたをしたもの、またはピクノメーターという専用のガラス器具を使って測定を行います。最初に、器具の乾燥質量 ![]() と体積 V (L) を測っておきます。
と体積 V (L) を測っておきます。

フラスコの中に適当量の試料を入れ、そのあと試料の沸点を超える温度 T (K) に保ちます。一定温度に保つためには恒温槽という、水や油あるいは砂などが入った装置を使います。この水や油あるいは砂を一定温度にしておいて、そこにフラスコを入れておけばよいのです。

しばらく放置すると、フラスコ内の試料は沸騰して気体となり、もともと入っていた空気は小さな穴から外に逃げ出していきます。フラスコ内は試料の気体で満たされて、圧力が大気圧より大きくなるので、空気が押し出された後は試料の気体が小さな穴から噴き出していきます。しばらくするとフラスコ内の圧力が大気圧 ![]() と等しくなり、気体の噴出が止まります。このとき、フラスコ内は、V (L)、T (K)、
と等しくなり、気体の噴出が止まります。このとき、フラスコ内は、V (L)、T (K)、 ![]() の気体で占められています。
の気体で占められています。

最後に ![]() を求めます。フラスコを冷却して室温にすると、試料が凝縮して液体となります。このときの質量を測定
を求めます。フラスコを冷却して室温にすると、試料が凝縮して液体となります。このときの質量を測定 ![]() して、そこから 最初に測定した乾燥質量
して、そこから 最初に測定した乾燥質量 ![]() を引くと、
を引くと、![]() が得られます。
が得られます。
このとき、室温まで冷却せずに測定してはいけません。
なぜなら、乾燥質量 ![]() には、フラスコ内の空気の質量も含まれているからです。
には、フラスコ内の空気の質量も含まれているからです。
冷却して気体が凝縮する前に測定すると、フラスコ内に空気が戻ってきていないので、空気の質量分が誤差になるのです。

これで必要な値を求めることができました。後は気体の状態方程式に求まった値を代入すると分子量が求まります。
![]() M について解いて、
M について解いて、 ![]()

【補正】
この気体の室温![]() における飽和蒸気圧を
における飽和蒸気圧を ![]() とすると、
とすると、 ![]() を測定した時点ではフラスコ内の空気の分圧は
を測定した時点ではフラスコ内の空気の分圧は![]() と大気圧より
と大気圧より ![]() だけ小さい。
だけ小さい。
従って、![]() は、本来の試料の質量より
は、本来の試料の質量より ![]() 、
、 ![]() 、V (L)の空気の質量分だけ少ないはずですね。
、V (L)の空気の質量分だけ少ないはずですね。
空気の平均分子量を0 M とすると、⑤の質量は次のように補正するべきです。
![]()
この値を用いると、分子量の補正値が次のように求められます。

デュマ法のまとめ

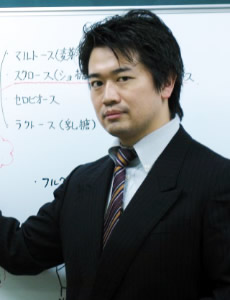
平野 晃康
株式会社CMP代表取締役
私立大学医学部に入ろう.COM管理人
大学受験アナリスト・予備校講師
昭和53年生まれ、予備校講師歴13年、大学院生の頃から予備校講師として化学・数学を主体に教鞭を取る。名古屋セミナーグループ医進サクセス室長を経て、株式会社CMPを設立、医学部受験情報を配信するメディアサイト私立大学医学部に入ろう.COMを立ち上げる傍ら、朝日新聞社・大学通信・ルックデータ出版などのコラム寄稿・取材などを行う。

